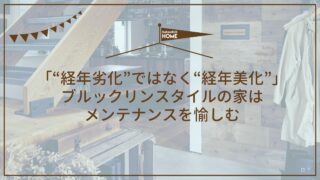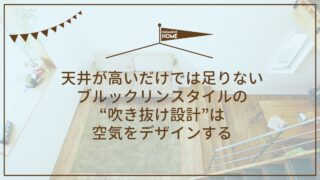「自分らしい家に住みたい」「理想の間取りを実現したい」と考えたとき、多くの人が思い浮かべるのが「注文住宅」です。しかし、いざ検討を始めてみると、「注文住宅って具体的にどんなもの?」「費用はどのくらいかかるの?」「デメリットや注意点は?」と、疑問や不安が次々と湧いてくるのではないでしょうか。
本記事では、注文住宅とはどのような住宅なのかを、建売住宅との違いやメリット・デメリットを交えながら、初心者にもわかりやすく解説します。また、注文住宅に向いている人・そうでない人の特徴や、費用相場、建築の流れ、後悔しないためのチェックポイントまで、網羅的に紹介します。
住宅の購入は一生に一度の大きな買い物です。情報が不足したまま契約を進めると、「思っていたのと違った」と後悔することにもなりかねません。この記事を読めば、注文住宅の特徴と建売との比較を踏まえ、自分にとって最適な住まいの選択肢が見えてくるはずです。
理想の住まいづくりに失敗しないために、まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。
「注文住宅を建てるなら自分らしい家を作りたい!」とお考えの方は、一度プロに相談してみませんか?ナカミチホームでは「完全予約制のモデルハウス」でお客様をお待ちしております。是非、お気軽にご相談下さい!


- 中通 一裕|ナカミチホーム代表取締役
- 岸和田を中心に南大阪エリアで長年家づくりに携わり、地域に根差した経験・知識・技術を培ってまいりました。お客様のライフスタイルに寄り添い、素材選びや間取り、動線、設備機能まで細部にこだわった提案を行うことが信条です。自然素材が持つ経年変化の魅力や、実際の住み心地を体感いただけるよう、定期的に見学会やショールームを開放し、安心してご相談いただける環境を整えています。これからも「快適で長く愛される住まい」を実現するために、きめ細やかなヒアリングとご提案を大切にしてまいります。
ナカミチホーム株式会社
注文住宅とは?建売・分譲との違いと種類を徹底解説
注文住宅とは、施主(家を建てる人)が土地の選定から建物の設計・仕様・設備に至るまで自由に決められる住宅のことです。自分や家族のライフスタイルや好みに合わせた間取りやデザインを選べることが大きな魅力です。対して建売住宅や分譲住宅は、すでに建築された住宅をそのまま購入する形式であり、間取りや仕様の変更がほとんどできません。
注文住宅には大きく分けて3つの種類があります。
注文住宅の定義と特徴とは?
注文住宅とは、間取り・内外装・設備・構造にいたるまで施主が細かく指定できる「自由設計」の家を指します。設計者と相談しながら、ゼロから自分たちの理想をかたちにしていくスタイルです。
その自由度の高さから「世界にひとつだけの家をつくりたい」という人に選ばれています。
また、土地がすでにある場合だけでなく、「建築条件付き土地」を購入してその条件に沿って家を建てるケースもあります。完全自由設計とまではいかないこともありますが、一定のカスタマイズが可能です。
建売住宅・分譲住宅との違いを比較
建売住宅とは、住宅会社や不動産会社があらかじめ設計・建築した一戸建て住宅を土地付きで販売する形式です。購入者は完成した家を内覧してから選べるため、「すぐに住める」「予算が明確」「手続きが早い」といった利点があります。
一方で、間取りや設備、デザインに対する自由度は低く、「家に自分たちが合わせる」というスタイルになります。
分譲住宅も同様に、一定の区画でまとめて建てられることが多く、コスト面や購入の手軽さが魅力ですが、個性を出しにくい側面もあります。
注文住宅は、これらと比べて「自由設計」「設計打ち合わせが必要」「完成までに時間がかかる」「コストが変動しやすい」といった特徴を持ちます。
注文住宅の種類|フルオーダー・セミオーダー・規格住宅とは
注文住宅には、以下のような3つのスタイルがあります。
- フルオーダー住宅:間取りから構造、素材、設備まで一からすべて指定できる最も自由度が高いタイプ。
- セミオーダー住宅:あらかじめ用意されたベースプランをもとに、部分的にカスタマイズ可能。
- 規格住宅(企画住宅):外観や設備などがある程度決まっているが、価格が抑えられ短納期で建てられる。
注文住宅=すべて自由に決められるというイメージがありますが、実際には予算・時間・労力とのバランスを取りながら、こうした種類の中から選ぶのが一般的です。
注文住宅と様々な種類を詳しく解説した「注文住宅の種類をわかりやすく解説|セミオーダーとフルオーダーの違いとは?」も合わせて読んで下さいね。
注文住宅のメリット5選|自由設計から満足度までわかる魅力
注文住宅の最大の魅力は、住む人の理想やライフスタイルに合った“世界にひとつだけの家”を実現できる点です。ここでは、注文住宅を選ぶことで得られる具体的なメリットを5つ紹介します。
間取りやデザインを自分で決められる自由度
注文住宅の中でもフルオーダー型は、間取りや外観、内装、さらにはコンセントの位置に至るまで細かく設計可能です。家事動線を意識したキッチン配置や、家族の会話が増えるリビング中心の設計など、自分たちの暮らしに合ったプランニングができます。こうした自由度の高さは、建売住宅ではなかなか得られない特権です。
家族構成やライフスタイルに合った住まいが実現できる
将来の家族構成やライフイベントに合わせて、最初から設計を柔軟に組み立てることができるのも注文住宅の強みです。例えば、リモートワークが多い人には書斎スペースを、子育て世帯には家事動線の短い間取りやリビング階段を設けるなど、ライフスタイルの多様性に応じた対応が可能です。
好みの設備・素材・住宅性能を選べる
注文住宅では、断熱性や耐震性など住宅性能にこだわった素材選びができます。フローリングの質感やキッチン・バスルームのメーカー選定まで自由に選べるため、暮らしの快適性やメンテナンス性にも優れた家づくりができます。近年では、ZEH対応や省エネ性を高めた設計も注目されています。
建築現場を見学・確認できる安心感
建築途中の現場に立ち会えるのは、注文住宅ならではのメリットです。工事の進捗を自分の目で確認し、不明点があれば担当者と相談することで、信頼関係の構築にもつながります。見えない部分にまでこだわりを持ちたい方にとって、非常に安心できるポイントです。
資産価値が下がりにくくリフォームにも柔軟に対応可能
注文住宅は個々の要望に基づいて設計されているため、機能性やデザイン性に優れ、長期的な居住満足度が高い傾向があります。また、将来的なリフォームや増築にも対応しやすい構造をあらかじめ組み込んでおけば、ライフステージの変化にも柔軟に対応できます。これにより、結果的に資産価値が下がりにくくなるケースも多いです。
「注文住宅を建てるなら自分らしい家を作りたい!」とお考えの方は、一度プロに相談してみませんか?ナカミチホームでは「完全予約制のモデルハウス」でお客様をお待ちしております。是非、お気軽にご相談下さい!

注文住宅のデメリット4選|契約前に押さえたいリスク
注文住宅は理想の住まいを実現できる一方で、特有のデメリットや注意点も存在します。憧れだけで判断してしまうと、思わぬトラブルや後悔につながることも。ここでは、注文住宅を検討する際に知っておくべき4つのリスクを紹介します。
建築期間が長く、入居まで時間がかかる
注文住宅はプラン設計から施工までの工程が多く、建売住宅に比べて入居までの期間が長くなる傾向があります。設計打ち合わせに1〜2か月、建築には平均6〜8か月かかるのが一般的です。土地探しから始める場合は、さらに数か月単位の余裕が必要になります。
このため、急いで引っ越したい方や引っ越しの期限が決まっている方には不向きな場合もあります。住み替えや仮住まいの準備も検討する必要があります。
費用が高く、予算オーバーのリスクもある
自由度が高い分、建材や設備のグレードアップ、オプションの追加などで当初の見積もりから費用がかさむケースが多く見られます。特に「せっかくなら…」という心理から、施主の希望が膨らみやすく、最終的に数百万円以上オーバーすることも。
注文住宅を検討する際は、必ず予算に上限を設けておくとともに、「本体価格以外の費用」(付帯工事・諸費用・税金など)を想定しておくことが重要です。
完成するまで仕上がりが見えにくい
注文住宅は図面やCGでの設計確認が中心で、完成品を事前に見ることができません。そのため、「思っていたより部屋が狭い」「窓の位置が不便」「外観がイメージと違う」など、完成後にギャップを感じるリスクがあります。
この問題を防ぐには、同じプランで建てられたモデルハウスの見学や、建築中の現場確認、シミュレーションツールの活用が有効です。
打ち合わせや決定事項が多く手間がかかる
注文住宅では、設備の仕様・床材・壁紙・収納・コンセント位置など、細かな部分まで施主が決める必要があります。打ち合わせの回数も多くなりやすく、仕事や子育てと並行して進めるのは負担に感じる人も多いです。
理想の住まいを実現するには、ある程度の“時間的・精神的な余裕”が必要です。信頼できる住宅会社や担当者との連携が、スムーズな進行の鍵になります。
注文住宅と建売住宅の違いを比較表でわかりやすく整理
「注文住宅と建売住宅、どっちが自分に合っているのか分からない」と悩む人は多いものです。ここでは、両者の違いをわかりやすく比較表で整理した上で、それぞれに向いている人の特徴を解説します。
自由度・価格・入居期間を比較表で整理
|
比較項目 |
注文住宅 |
建売住宅 |
|
設計自由度 |
高い(間取り・素材・設備を自由に選択可能) |
低い(決められた間取り・仕様) |
|
価格の目安 |
高め(仕様次第で変動) |
比較的リーズナブル(固定価格) |
|
建築期間 |
平均8か月以上(プラン〜引き渡し) |
即入居可能(完成済み) |
|
建築過程の確認 |
可(施工中も見学可能) |
不可(完成済み) |
|
設備・仕様の選択 |
自由に選べる |
選べない(既製) |
|
デザインの個性 |
出しやすい |
出しにくい(画一的) |
|
住環境の調整 |
自分で土地選びから可 |
業者の設定済み土地 |
|
リフォーム適応 |
柔軟に対応しやすい |
間取り次第で制限あり |
注文住宅は自由度が高く、自分らしい暮らしを追求したい人に最適。一方で、建売住宅は手間を省きたい人や、すぐに入居したい人に適しています。
注文住宅が向いている人の特徴とは?
- こだわりの間取りやデザインを実現したい人
- 家族のライフスタイルに最適な動線を設計したい人
- 長く住むことを前提に、資産価値や快適性を重視したい人
- 自分で土地を探したい、もしくはすでに所有している人
- 建築過程も確認したい、信頼できる会社と相談したい人
このような方には、多少手間がかかっても満足度の高い住まいをつくれる注文住宅が向いています。
建売住宅が向いている人の特徴とは?
- 時間が限られており、すぐに住みたい人
- 打ち合わせや決定事項が多いのが苦手な人
- 予算を明確にして、総額を固定したい人
- モデルハウスで完成形を見てから決めたい人
- 「一般的な使いやすい間取り」で十分という考えの人
建売住宅は「コストパフォーマンス重視」や「手間をかけずに住宅購入したい」というニーズに合致します。
注文住宅と建売住宅の違いは「注文住宅と建売住宅の違いを徹底比較|選び方・価格・メリットを解説」で詳しく解説していますので合わせて読んで下さい。
注文住宅の費用相場と予算の立て方|内訳と注意点も解説
注文住宅を建てるにあたり、最も気になるのが「いくらかかるのか」という費用面です。ここでは、注文住宅にかかる総額相場、費用の内訳、そして予算の立て方について詳しく解説します。
注文住宅の総額相場と価格帯別の違い
注文住宅の建築費用は、土地の有無や建物の規模、設備グレードによって大きく変動します。一般的な価格帯の目安は以下の通りです。
|
建築パターン |
費用相場(建物のみ) |
|
ローコスト住宅 |
約1,500万〜2,000万円 |
|
一般的住宅 |
約2,000万〜3,000万円 |
|
高性能住宅 |
約3,000万〜4,500万円 |
ここに土地代が加わると、総額は4,000万円前後になるケースも多く、地域や条件により変動します。特に都市部では土地価格が高騰する傾向があるため、早い段階で「建物+土地」の予算配分を意識することが重要です。
建物本体工事・付帯工事・諸費用の内訳とは
注文住宅の費用は、大きく3つの構成に分けられます。
- 本体工事費:基礎・構造・屋根・内装などの建物そのものにかかる費用(約70%)
- 付帯工事費:外構、給排水、電気工事、地盤改良など(約15%)
- 諸費用:設計料、登記費用、ローン手数料、火災保険、税金など(約15%)
見積書を受け取ったら、「本体工事費だけで判断せず、総額ベースで比較する」ことがポイントです。追加工事や変更によって大きくズレが生じることもあるため、契約時には費用項目を細かくチェックしましょう。
土地代や住宅ローンの考え方
土地付きで建てる場合は、建物以上に土地代の比率が高くなることもあります。都内や駅近エリアでは、土地だけで2,000万円を超えるケースも。
また、注文住宅では「つなぎ融資(中間金)」が必要になる場合があり、金融機関やローン商品によって支払いスケジュールが異なります。ローン契約前にはつなぎ融資の有無と条件を必ず確認しましょう。
年収から見た予算の目安と資金計画の立て方
一般的に、住宅ローンの借入額は「年収の5〜6倍」が目安とされますが、無理のない返済を考慮すると年収の4倍以内に抑えるのが安全です。たとえば、年収500万円の場合、建物+土地の予算は2,000万円程度がひとつの基準になります。
また、自己資金(頭金)を用意することで、金利や返済額を抑えることができ、審査にも通りやすくなります。自己資金+借入可能額+補助金制度をフル活用して、バランスの良い資金計画を立てましょう。
注文住宅を建てる流れとスケジュール|全12ステップでわかる進行手順
注文住宅の魅力を最大限に活かすには、あらかじめ「どのような流れで家が建つのか」を把握しておくことが重要です。ここでは、初期の相談から完成・引き渡しまでの全12ステップを時系列で解説します。
1. 理想の住まいイメージを明確にする
まずは家族で「どんな暮らしがしたいか」「どんな家に住みたいか」を話し合い、理想の間取り・デザイン・立地条件などをリストアップします。PinterestやSNS、住宅雑誌などでイメージを具体化しておくと、後の打ち合わせがスムーズに進みます。
2. 情報収集と見学
インターネット検索や住宅展示場、モデルハウスなどを活用して情報収集を行います。ハウスメーカーや工務店ごとに特徴が異なるため、見学を通じて「自分たちに合うパートナー」を見極めましょう。
3. 資金計画と住宅ローン事前審査
予算に応じた資金計画を立てます。あわせて住宅ローンの借入可能額を把握し、必要に応じて事前審査を受けておくことで、土地や建築のタイミングを逃さずに進められます。
4. 土地探し(または土地の活用)
注文住宅を建てる土地が未定の場合は、エリアや価格帯を絞って土地を探します。地盤調査や周辺環境の確認も忘れずに行いましょう。既に所有している土地を活用する場合も、建築条件や法規制の確認が必要です。
5. ハウスメーカー・工務店選定
予算・設計の自由度・施工実績・アフターサポート体制などを基準に、依頼先を絞り込みます。複数社に相談することも可能ですが、最終的には1社に決定し、パートナーシップを築いていくことが大切です。
6. プランニング・見積もり・契約
要望に応じた設計プランと見積もりが提示されます。この段階で打ち合わせ回数が多くなりやすく、設備や間取りの調整が入ります。納得のいくプランが完成したら、工事請負契約を締結します。
7. 住宅ローン本申し込み・各種手続き
契約後、住宅ローンの本申し込みと同時に、登記・火災保険・保証制度などの手続きも進めます。スケジュール通りに進めるためには、金融機関や登記関連のスムーズな対応が不可欠です。
8. 着工(基礎工事〜上棟)
地鎮祭を終えたら、いよいよ工事がスタートします。基礎工事→配管工事→上棟(柱や梁の設置)という順に進み、家の骨格ができあがります。定期的に現場を見学し、進捗や仕様の確認を行うと安心です。
9. 各種内装・外装工事
断熱材や壁材、設備の取り付け、外壁・屋根の仕上げなど、細かい工程が続きます。この段階での「追加オプション」や「仕様変更」は費用増加や工期遅延の原因になるため注意しましょう。
10. 竣工・完了検査
建物が完成したら、施工業者・第三者機関による完了検査が実施されます。間取りや設備に問題がないか、施工ミスがないかをチェックし、不備があれば手直しが行われます。
11. 引き渡し・入居準備
鍵の受け取りとともに、建物の引き渡しを受けます。引っ越し準備やインフラ(電気・ガス・水道)の手続き、家具・家電の搬入スケジュールもこの時期に集中します。
12. アフターサポート・メンテナンス
入居後は、定期点検やアフターサービスを受けることで、住まいを長持ちさせることができます。特に住宅性能保証制度や長期保証の内容は、契約前にしっかり確認しておくことが肝心です。
注文住宅完成までの流れを詳しく解説した「注文住宅の流れを完全ガイド|土地探しから契約・完成までやさしく解説」も合わせて読んで下さいね。
まとめ|注文住宅の魅力とリスクを理解して理想の住まいを実現しよう
注文住宅は、自分たちのライフスタイルに合わせた“理想の家づくり”を叶えられる点で、非常に魅力的な選択肢です。自由な間取り設計や設備の選択、デザイン性など、他にはない「オンリーワンの住まい」を実現できる反面、予算や時間、労力といった課題も存在します。
本記事では、注文住宅とは何かという基本から、メリット・デメリット、建売住宅との違い、費用相場や建築の流れまで網羅的に解説しました。
注文住宅の成功のカギは「しっかりとした情報収集」と「信頼できるパートナー選び」です。焦らず、ひとつひとつのステップを確実に踏むことで、満足度の高い家づくりが実現できます。
これから家づくりを始める方は、本記事の内容を参考に、自分たちにとって最適な住まいのかたちを見つけてください。
ナカミチホームでは「おしゃれと機能性を兼ね備えたモデルハウス」を展示中!
- どんな間取りがいいの?
- 資金計画はどうすればいいの?
- おしゃれで機能的な家は実現できるの?
こんなお悩みを完全予約制の「モデルハウス(築65年の公民館をリノベーションして、家具まで揃う新しい規格住宅を建てました)」でゆっくり相談してみませんか?是非お気軽に予約下さい。心よりお待ちしております。
\来場予約でスタイルブックプレゼント中/